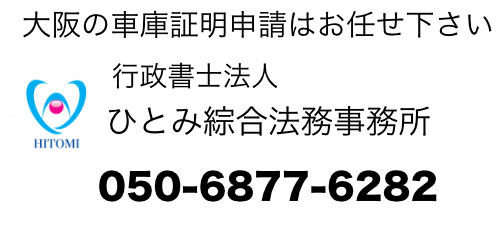自動車の保管場所が必ずしも駐車場の為に用意した土地でなくても、車庫証明申請はできます。もちろん公道や、自分に使用する権限のない土地を保管場所としての申請はできません。
また、車を止めるスペースがない空間も当然ながら申請は無理です。ではそれらに該当しない土地であれば保管場所(駐車場)として全て大丈夫かといえば、そうではありません。
実はそれぞれの土地や区域によって、車を十分に止める事ができるにもかかわらず、車庫証明が申請できない区域というものが存在します。
これはそのひとつの例です。
大阪市中央区の船場建築線
大阪の東警察が管轄する地域での話です。
東警察の管轄区域は、「大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域」とされています。
この管轄の中には、旧市街地建築物法第7条ただし書きに基づき、【船場建築線の指定】を受けている地域が存在します。
船場建築線について詳しくはこちら
→大阪市:建築基準法上の道路種別と道路判定等 (…>建築基準法の概要など>建築基準法上における道路の種類及び判定)
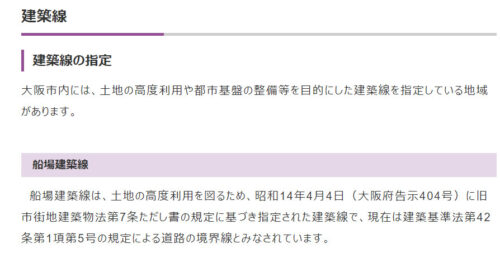
現在どの範囲の地域が船場建築線の指定かは、こちらのPDFで確認する事が出来ます。
→船場建築線の指定状況
建築基準法に基づく建物の建築の制限云々については、今回の主題と違いますので、ひとまず置いておきます。
問題はこの指定と車庫証明がどう関係するのかというところです。
船場建築線と車庫証明
船場建築線の指定の内容は以下のようになっています。
船場建築線についてのQ&Aより引用
船場建築線は、概ね南北方向の道路については、その中心より5m、東西方向の道路については、6m後退した位置に指定され、建築線が交差する部分についても、2.5mのすみ切り(街角剪除)を行う形に指定されています。(一部上記の説明と異なる箇所がありますので、詳しくは「船場建築線指定図」でお確かめ下さい。)
なお、建築線は、土地の所有権とはかかわりなく指定されたものである点にご注意下さい。
ざっと読むだけだと何の事か分かりにくいので、簡単に説明します。
- 南北に走る道路に面していれば道路中心部より5m
- 東西に走る道路に面していれば道路中心部より6m
以上のようにそれぞれ道路の中心線より一定の距離が離れているスペースでなければ、どれほど空間があっても(この地域は道路の脇はたいてい歩道なのでスペースはあります)車庫証明を取得する事ができません。
例えば、南北に走る道路に面しているスペースを駐車場として車庫証明の申請をするつもりであれば、そこは道路の中心より必ず5m以上離れていなけれななりません。
この指定を受けている区域は、碁盤目上に整理されているので南北に走る道路の幅はほぼどこも5m、つまり中心部から道路との境界までは2.5mあります。従ってその道路との境界から更に2.5m間隔が開いている必要があるのです。
駐車場のスペースがこれより手前にあると、申請が通りません。大阪東警察署の申請窓口では、車庫証明の申請時にこの点を相当確認されます。あまりにもあやふやだと申請自体を一端保留する事もあります。何しろ一度申請してみて通らなかった場合、書類は返ってきませんので。
いずれにしても、配置図作成の時にかなり注意して測量する必要があります。
船場建築線を気にしなくてもいい駐車場
ただ、このスペースというのは別に車を止めてはいけない場所ではありません。
車庫証明における「車の保管場所」としては使えないというだけです。
従って、例えば喫茶店などの駐車スペースとしてや、コインパーキングなどのように、車庫証明とは関係のない駐車スペースとして利用する分には全く問題ないのです。
実際このあたりはビジネス街ということもあり、コインパーキングはものすごく多いです。